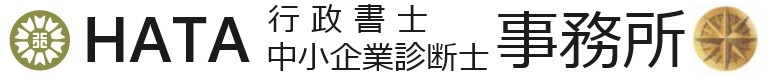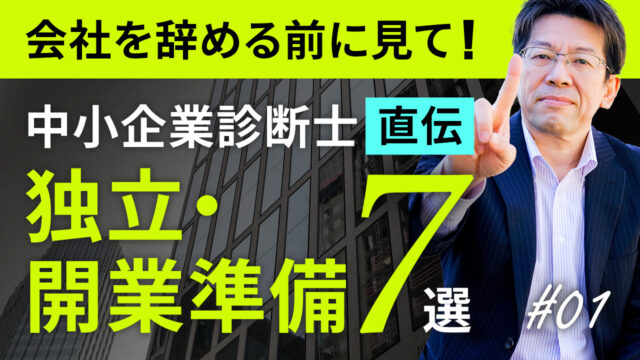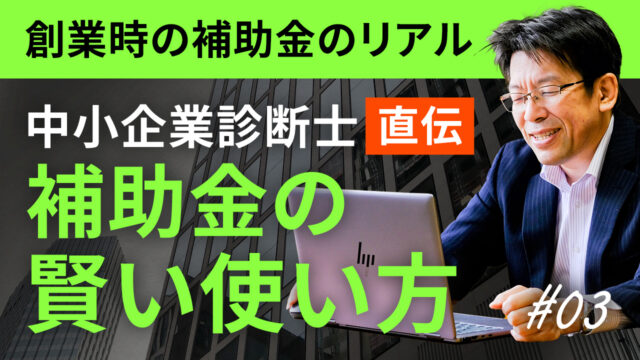退職してから独立開業を考えている方にとって、いざ開業してからやることが山積みでは、思うように営業活動や売上作りに集中できません。実は「開業してからやればいい」と思っていた手続きの多くは、退職前から準備できるんです。
この記事では、退職前にこっそり進めておくことで、開業後が驚くほどスムーズになる「5つの準備」について、実体験と支援現場でのアドバイスを交えて解説します。
1. 副業から始めて事業の土台をつくる
「いきなり会社を辞める」前に、副業で小さく始めることをおすすめします。たとえ本業と関係ないジャンルでも構いません。まずは収入を得る経験を積むことで、会計や資金調達など、開業に必要な実務に触れられるからです。
飲食ならシェアキッチン、美容業なら間借り営業など、最近は副業向けの環境も整っています。就業規則の確認は必要ですが、本気で開業したいなら今から動き出す価値は十分にあります。
2. 開業届と青色申告の手続きをしておく
副業で収入が出たら、開業届を出して青色申告の承認申請も行いましょう。これは帳簿を付けるための第一歩です。
「20万円以下なら申告不要」と言われることもありますが、むしろきちんと開業届を出し、会計知識を身につけておくことで、後々の補助金申請や融資の準備にもなります。
3. 会計ソフト・専用口座・カードの導入
会計ソフトの導入や、事業用の口座・カードの準備も、できる限り早めに。特に副業段階から経理を分けておくことで、開業後の処理が格段に楽になります。
財布を2つ持って現金の管理を分けるなど、習慣レベルで分離できていれば、あとから困ることもありません。
4. 創業計画書を作って事業の整理を
創業融資や資金調達に必要な創業計画書ですが、実は開業前に作っておくと「自分の頭の整理」にもなります。
誰に何をどう売るのか、必要な資金はいくらか、どのくらい売れる見込みか…。こうしたことを紙に落とし込むだけでも、事業の解像度がぐっと上がります。
商工会議所や日本政策金融公庫では、作成相談にも乗ってくれるので、退職前から通っておくのがおすすめです。
5. 補助金の事業計画を早めに準備
補助金は開業後すぐには使えないことが多く、事前の準備が非常に重要です。特に「持続化補助金(創業枠)」を活用するなら、事前に「特定創業支援」を受けておく必要があります。
また、補助金申請には詳細な事業計画書が必要で、商工会議所と何度かやり取りが必要になります。方向性が決まってからでないと修正が難しいため、開業直前よりも早めの準備がベストです。
【まとめ】
退職前からできる準備をしておくことで、開業後の負担は大きく軽減されます。特に「副業→開業」という流れは、実績や信用、申請上の加点にもつながります。
商工会議所やよろず支援拠点も活用しながら、失敗のないスタートを切っていきましょう。
お気軽にお問合せください。

HATA行政書士・中小企業診断士事務所
お気軽にお問合せください。
当事務所は、安楽寺内にあります。代表が運営しているコワーキングスペースが隣接しています。