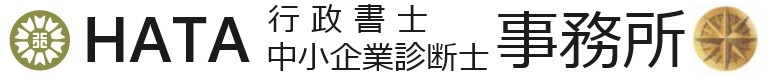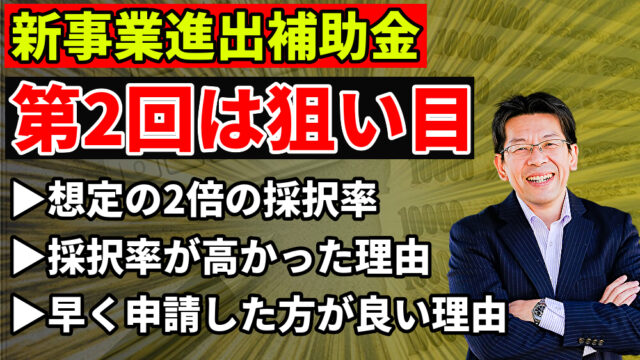補助金の採択結果を見ると、製造業の採択率が比較的高い状態が長く続いています。
一方で、飲食業や宿泊業などのサービス業は、どうしても採択率が低く出ることが多く、
「業種的に不利なのでは?」と感じてしまう方も少なくありません。
この記事では、中小企業診断士・行政書士として多数の補助金申請を支援してきた立場から、
- 製造業が補助金に強い理由
- 審査側が重視しているポイント
- 製造業以外の業種でも採択率を上げる方法
について、実例を交えてわかりやすく解説します。
1. 製造業の採択率が高い3つの理由
① 経済波及効果が大きい
補助金は「事業者を儲けさせるため」ではなく、経済全体へ波及させるための投資です。
製造業の場合、設備を導入すれば、
- 発注元企業
- 下請け企業
- 関連事業者
など、関わる事業者が多いため、投じた税金に対するリターンが大きくなります。
これは審査上、非常にプラス要素になります。
② 投資内容の妥当性が判断しやすい
製造業の設備(例:マシニングセンタ、旋盤など)は相場が明確で、
高額投資でも不正の余地が少ないと判断されやすい傾向があります。
一方、飲食・宿泊業では「内装工事」が多く、
“見積の妥当性”が判断しにくいという特徴があります。
そのため、審査側としては製造業の方が評価しやすい構造になっています。
③ 成果が数値で説明できるため審査がしやすい
製造業では、取り組みの成果を数値で示しやすいのが強みです。
- 加工精度の向上
- 長尺製品の対応
- 生産能力の向上
- 不良率の減少
など、数字で比較できる成果は補助金と非常に相性が良い要素です。
●例
「1メートルの製品 → 3メートルに対応可能になる」
「生産時間が30%短縮できる」
審査員側が読み取れる“客観的な変化”があるかどうかは重要なポイントです。
2. 他業種でも採択率を上げるためのポイント
製造業の強みを理解すると、逆に他業種でもやるべきことが明確になります。
特に飲食業・宿泊業は数が多く、差別化が難しいため、
以下の点を強く意識することで採択率は大きく上がります。
① 他社と比較可能な「数値」を計画書に入れる
飲食業の場合、「美味しくなります」「高級になります」では差になりません。
- 回転率
- 提供時間
- 品質の安定性
- 客単価
など、数字で比較可能な指標を必ず入れましょう。
② 地域性・独自性を出す
飲食・宿泊は全国に大量にあるため、「どこでもできる内容」は弱くなります。
- 地域でしか手に入らない食材
- 地元の文化・イベントとの連携
- 地域特有の観光ニーズ
自治体が推しているテーマと結びつけると採択率が上がります。
③ 経済波及効果を広く示す
「自社が儲かる」だけではNGです。
- 地元の仕入先
- 新たに関わる事業者
- 地域経済の活性化
- 雇用への貢献
など、周囲へのプラス効果をしっかり記載することが重要です。
④ 加点を確実に積み上げる
業種的に不利な場合、加点の積み上げが採択を左右します。
- 事前着手の禁止への遵守
- 賃上げの表明
- インボイス登録
- 経営力向上計画
- 経営革新計画
新事業進出補助金は特に加点が取りやすいため、ここは取りこぼさないことが重要です。
3. 実際の支援事例:飲食・宿泊業でも採択されている
私が直近で支援した6件のうち、5件が飲食・宿泊業でしたが、
そのうち4件が採択されました。
製造業と同じ考え方を取り入れることで、
サービス業でも十分に採択可能です。
4. まとめ
- 製造業は補助金の構造上、有利になりやすい
- しかし、他業種でも“戦い方”を理解すれば採択は狙える
- 数値化・独自性・経済波及効果・加点の4軸が重要
補助金は業種で諦める必要はありません。
計画の作り方次第で採択率は大きく変わります。
補助金の相談はお気軽にどうぞ
私の事務所では、
- 新事業進出補助金
- ものづくり補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- 事業再構築補助金(※現在は制度終了)
など幅広く支援しています。
公式LINEでの問い合わせも可能ですので、
まずはお気軽にご相談ください。
お気軽にお問合せください。

HATA行政書士・中小企業診断士事務所
お気軽にお問合せください。
当事務所は、安楽寺内にあります。代表が運営しているコワーキングスペースが隣接しています。