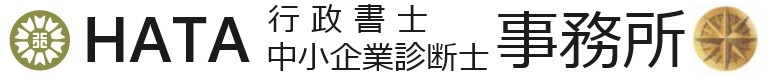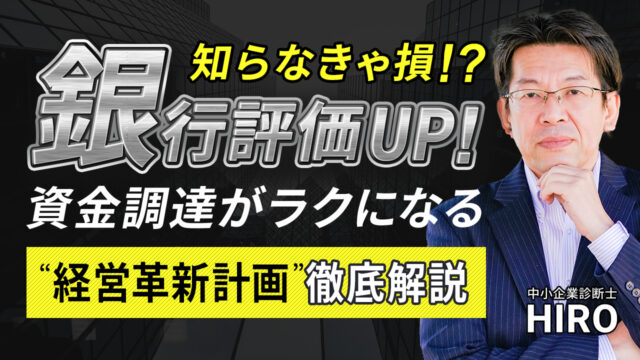今回は、ものづくり補助金・第19次公募における「事業計画書の作り方」について、詳しく解説していきます。すでに公募がスタートしており、今回からの大きな変更点として電子申請による入力方式が導入され、事業計画書の作成が非常に複雑になっています。
実際に書いてみると「これ、どう書けばいいの?」と感じる方も多いはず。そんな方のために、今回は記載のコツや注意点を整理してお届けします。
1. 今回の変更点と全体構成の理解
- Word形式で10ページ程度の自由記載だった以前と異なり、今回は電子申請画面に沿った構造化された入力が必要。
- 各項目には文字数制限(最大1000文字)があり、重複を避けて記述する必要あり。
- 給与支給総額や賃金引上げ要件の厳格化により、計画の実現可能性がより重要に。
2. 事業計画書の記載項目とコツ(1〜9)
① 事業実施の背景
- 外部環境(市場・顧客ニーズ・トレンド)
- 内部環境(自社の資源・体制・技術・実績)
- 強み・弱みの明確化
- 解決すべき「課題」=今回の事業で解決する対象
✏️「なぜ今、これをやる必要があるのか?」を明確に。
② 会社全体の事業計画
- 経営理念・中長期のビジョン
- 各事業の位置づけと展開方針
- 今回の事業が会社全体の中でどう位置づけられるか(メイン?補完?)
✏️「自社の未来の地図」と「その中にある今回の役割」を描く。
③ 補助事業の具体的アクション
- 事業の具体的な中身(開発内容、サービス内容)
- 誰が/いつ/何を/どのようにやるのか(工程・体制・KPI)
- 必要な能力・資金・体制があることの証明
✏️「やるべきこと」と「できる根拠(リソース)」をセットで書く。
④ 事業に要する経費とその必要性
- 必要な設備や開発費の内訳
- なぜそれが必要か(事業との関係性)
- 型番・スペック・他社との差異(特に機械装置)
- 補助対象/対象外の明確化
✏️「この投資がなければ実現できない」ことを示す。
⑤ 革新性・差別化ポイント
- 他社にはない特徴・工夫(サービス・技術・仕組み)
- 競合との比較分析(何が違う?なぜ強い?)
- 自社のノウハウ・強みの活かし方
✏️「ウチにしかできない」部分を全面に出す
⑥ 市場への影響・ニーズの根拠
- 市場のニーズ・動向・規模・成長性
- 対象ユーザー・販売計画・価格・収益性
- 付加価値増加(売上-原価+人件費+減価償却)のシナリオと根拠
✏️「マーケットにどう食い込むか」を、数字で示す。
⑦ 賃金引き上げの計画
- 上記⑥の成果を踏まえて
- 賃金(総額・1人あたり・最低賃金)の引上げ計画
- 実現可能性のある内容(無理な目標NG)
- ✏️「ウチの会社も良くなる」ことを明確に。
⑧ 地域への貢献
- 地域特性と地域に対する経済的波及効果
- ニッチ分野における差別化
- 異なる事業者との連携や事業紹介
- 先端的デジタル技術の活用など
- 成長と分配の好循環
- ✏️審査項目の「政策面」に沿って書く
⑨ グローバル展開(該当者のみ)
- 5項目(進出国・市場分析・現地連携など)を1000文字以内で記載
- 補足資料・エビデンス資料が求められるため注意
3. 補足資料の作成ポイント
① 補助事業のスケジュール
- 申請〜交付決定〜発注〜完了までを記載
- 機械装置の発注は交付決定後(9月以降)を前提に作成
- Excelでの作成も可能
② 実施体制図
- 現状の体制と新事業の実施体制をビジュアル化
- どのチームが何を担うかを明示
③ 事業全体のイメージ図
- ビジネスモデルや事業の流れ図を作成し、①〜⑨の内容と整合性を持たせる
4. 注意点とよくある落とし穴
- 給与支給総額:役員と従業員で分けて記載が必要。返還リスクがあるため高すぎる目標設定は危険。
- 文字数制限:各項目1000文字以内。要点を絞って記載しないとオーバーしやすい。
- 経費の理由付け:単に必要というだけでなく「なぜそれがなければ実現できないか」を明確に。
- 電子申請の操作性:未確定な部分もあるが、数値や成長率の計算Excelなどは公式HPに用意されている。
最後に
今回の内容は、あくまで一例であり、事業内容によって書き方は変わってきます。
ブログでは、動画で話した赤字ポイント(書き方のヒント)もそのまま掲載していますので、繰り返し確認したい方はブックマークして活用してください。
もし「ここがわからない」「この辺を詳しく聞きたい」ということがあれば、コメントやお問い合わせからどうぞ!
引き続き、補助金や経営支援、士業の活かし方など、実務に役立つ情報を発信していきますので、チャンネル登録・高評価・シェアよろしくお願いします!
お気軽にお問合せください。

HATA行政書士・中小企業診断士事務所
お気軽にお問合せください。
当事務所は、安楽寺内にあります。代表が運営しているコワーキングスペースが隣接しています。