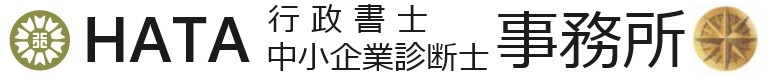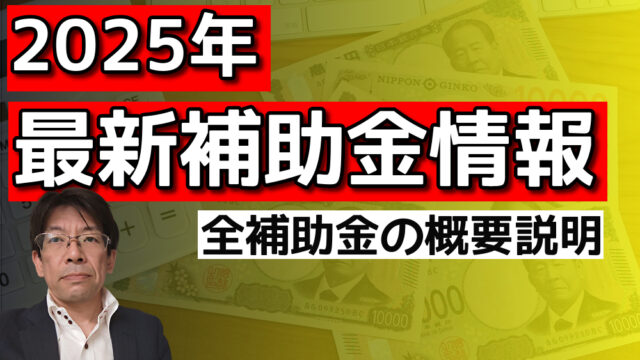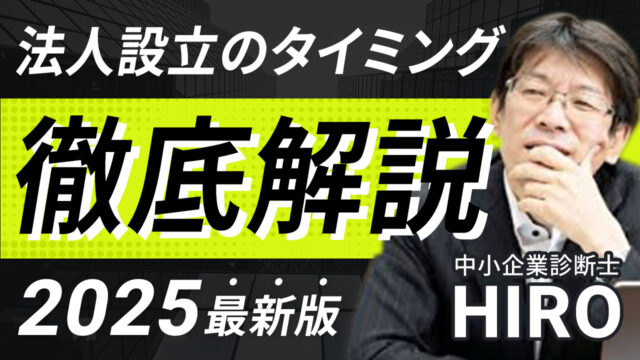今回は「補助金に不採択される理由」について詳しく解説します。これまでに累計30〜40件、補助金額にして3億円近くの支援を行ってきた実績をもとに、不採択の原因とその対策を具体的にお伝えします。
1. 公募要領の理解不足
不採択理由
多くの事業者が直面する最大の原因は「公募要領を十分に理解していない」ことです。補助金ごとに公募要領は異なり、各申請枠に求められる要件や必要書類が細かく記載されています。
対策
- 公募要領は1回だけでなく何度も読み直し、各申請枠に応じた要件を確認する。
- 必要書類リストをチェックリスト化し、提出漏れを防ぐ。
- 専門家(中小企業診断士など)に事前確認を依頼する。
2. 書類不備と要件未達
不採択理由
申請書類に不備がある場合や、補助金の基本要件を満たしていない場合は、自動的に不採択となることが多いです。特に「ものづくり補助金」や「事業再構築補助金」では、給与支給額の増加や付加価値額の増加など、数値的な要件が求められます。
対策
- 電子申請システム上でエラーが出ないよう、事前に試験入力を行う。
- 「給与支給総額」や「付加価値額」の根拠を明確に説明する。
- 類型や申請枠ごとに求められる要件を正確に把握する。
3. 補助金の趣旨と投資内容の不一致
不採択理由
補助金にはそれぞれ目的や趣旨があります。「ものづくり補助金」は設備投資、「持続化補助金」は販路開拓、「事業再構築補助金」は新市場進出がテーマです。この趣旨に沿わない計画は、不採択となる可能性が高いです。
対策
- 各補助金のテーマを理解し、事業計画をその趣旨に沿って構築する。
- 例えば持続化補助金では「新しい顧客層を増やす施策」を強調する。
- 宣伝費などの経費が過剰にならないよう、バランスを意識する。
4. 事業計画の不備(論理性・数値根拠の欠如)
不採択理由
事業計画が論理的でなく、数値的根拠が不足しているケースも不採択の原因です。審査員は限られた時間で申請書を読み、採点します。その際、ストーリーが一貫していないと評価が低くなります。
対策
- 事業のニーズ、解決方法、投資内容、期待される成果を明確に説明する。
- 数字に基づいた根拠を示し、将来の売上や利益の見込みを具体的に記載する。
- 経費の明確化と、なぜその経費が必要かを論理的に説明する。
5. 資金調達計画の不十分さ
不採択理由
補助金は後払いであり、事前に自己資金または融資を確保しておく必要があります。資金調達計画が不十分だと、事業の実現可能性が低いと判断され、不採択につながります。
対策
- 金融機関と事前に相談し、補助金採択時の融資確約を得る。
- 現在の自己資金状況を明記し、資金繰り計画を提示する。
6. 事業規模と計画のミスマッチ
不採択理由
現在の事業規模に対して、補助金申請額が過大な場合、実現可能性に疑問を持たれることがあります。例えば、年商1000万円の企業が3000万円の設備投資を申請する場合、売上の伸びを具体的に説明できないと不採択になりがちです。
対策
- 現在の事業規模に即した申請金額と事業計画を立案する。
- 投資後の売上・利益増加のシナリオを具体的に示す。
7. 加点項目を見落としている
不採択理由
補助金申請では、加点項目を取得することが採択率を高める重要な要素です。例えば「経営力向上計画」や「事業継続力強化計画」など、申請前に簡単に取得できる加点項目を見落とすと、他の申請者に比べて不利になります。
対策
- 公募要領の「加点項目」をチェックし、取得可能なものは必ず申請前に準備する。
- 経営力向上計画や事業継続力強化計画の策定を進める。
8. 社会的意義の不足
不採択理由
補助金は公的資金であり、その投資が社会にどのような貢献をもたらすかも重要な評価基準です。社会的意義が薄いと、採択率が低下します。
対策
- 地域経済への貢献、雇用創出、環境への配慮など、事業の社会的意義を強調する。
- エステやシミュレーションゴルフのような事業でも「地域活性化」「健康促進」などの切り口を用いて意義を伝える。
まとめ:不採択を防ぐためにできること
補助金申請で不採択を避けるには、以下のポイントを徹底することが重要です。
- 公募要領を熟読し、各申請枠の要件を理解する。
- 必要書類を漏れなく提出し、記載内容に誤りがないか確認する。
- 事業計画を論理的かつ数値的根拠をもって作成する。
- 資金調達計画を事前に立て、実現可能性を示す。
- 加点項目を取得し、他の申請者と差をつける。
補助金申請は事業計画の精度と準備が鍵を握ります。不安な場合は専門家の力を借りることも有効です。補助金を上手に活用して、事業成長を実現しましょう!
お気軽にお問合せください。

HATA行政書士・中小企業診断士事務所
お気軽にお問合せください。
当事務所は、安楽寺内にあります。代表が運営しているコワーキングスペースが隣接しています。